記事を翻訳してるサイト無いのでここで投稿していこうと思います。
2021.3.04にランチャーに投稿された記事の翻訳です。
※誤訳がある可能性があります
指揮官諸君!
本日は、ストーリーの更新をご用意しました。これまでのストーリーは、このまとめで読むことができます。
・これまでのストーリー
2020年代後半。数十年にわたる繁栄の後、西洋文明は一転して10年にわたる争いと内乱の時代を迎えていた。かつては平和が支配していたが、今や紛争が日常となり、ヨーロッパやアメリカでは、伝統的な政治勢力と新しく出現した貪欲で悪質な企業との間の支配権争いに徐々に飲み込まれ、物事が崩壊し始めている。
しかし、そんな新世界の巨人たちの中にも、超然としたトレンド予測能力で知られる21世紀の伝説的投資家、デビッド・マードックのような傑出した人物もいる。最近、彼は全く新しいベンチャー企業 "ペリヘリオン "を設立したが、その目的は謎めいたオーナーの経歴と同様にミステリアスである。
あなたはサミュエル・ソープ。ドバイで失敗した仕事の責任を取って、運の悪い傭兵だ。シカゴに亡命し、怒りにまかせて考えていたあなたの前に、面接の招待状が舞い込んだ。数々の厳しいテストをクリアしたあなたは、マードックとのディナーに招待されることになった。マードックは側近のノラ・ファーガソンとともに、自分の計画、少なくとも自分の役割を君に明かした。近年、各大企業は権力を誇示する手段を育成しており、通常は武装した傭兵部隊という形をとっている。その規模は、精鋭部隊の数小隊から、歩兵装甲部隊の1個師団まで、実にさまざまである。このような私設部隊は米軍の力にはかなわないが、その傾向は明らかだ。世界中の政府上層部に腐敗と無能が蔓延し、民主主義の時代は終わりを告げ、企業の時代が始まろうとしているのだ。
マードックは、並外れた先見性で、このような組織の必要性を認識していた。結局のところ、金そのものにできることは限られており、真の権力は常に、開いた手のひらではなく、握りしめた拳から生まれるのである。彼は、現在アリゾナ砂漠にある彼の臨時キャンプにいる軍隊を訓練するために、あなたを雇いました。そして、ファーガソンに君を託した。
その道中、あなたはマードックの巨額の資産だけでなく、米軍とのつながりも知ることになる。マードックは、明らかにアメリカの体制に深く入り込んでおり、アメリカの繁栄を願っているのだ。
事実上のリーダーであるゲイル・エスピノザは、君を自分の地位を脅かす存在と見ている。その結果、装備や編成に問題があると判断し、あなたを攻撃して気絶させる。幸いにも、その日のうちに事態は平和的に解決し、本当の意味でのトレーニングが始まる。
そして、その続きです。
2028年7月、アリゾナ州
夜空は早朝の深紅に染まっていた。夜が明けても私は焚き火のそばに横たわり、パチパチと柔らかく燃える音や、ゆっくりと目覚める軍事キャンプの音に耳を傾けていた。ガソリンの焦げたような悪臭がいつまでも漂い、早起きした鳥が持って歩くコーヒーの甘い香りと混じり合っていた。ある瞬間、すべてが静かになり、数分後には足音だけが聞こえてきた。

あのゾンビたちはどこから突然やってきたのだろう、と混乱した騒ぎを見ながら思った。もしかしたら、ウイルスに感染したのかもしれない。そうだとしたら、起きる意味がないじゃないか。
しかし、そんなことはない。ゾンビらしくないフレンドリーなあいさつをされただけで、私の望みは絶たれた。
数時間後、そして数冊の雑誌を手にしたとき、その知らせが届いた。
銃の手入れを終えようとした時、明らかに動揺しているエスピノザが庭の向こうから手を振ってきた。今度は何だろうと思いながら、手に残った油分を洗い、テントカバーの外に立っている空の銃身に雑巾を投げつけた。
私は、キャンプの端にある司令部へ向かった。テントというより、キャンバスやプラスチック、板金でできた半永久的な構造物で、弧を描く屋根がより広い空間を演出していた。そのため、多くの人が外の寝床に寝泊まりし、温室のような暑さよりも近くの川で虫に刺されることの方を好んだ。
ジム・トゥークローズ(Jim Twocrows)はすでに中にいて、地図やフォルダー、洗っていないコーヒーカップなどでいっぱいの大きな金属製の机の真ん中にある通信用ノートパソコンを熱心に見ている。ここは、通信担当の小柄なアイオワ人、マーカス・アバナシー(Marcus Abernathy)の王国であり、誰も足を踏み入れる勇気のない場所だった。
「どうしたんだ、マーク!」。と、私はドアから挨拶した。
彼は、いつもと同じように不機嫌な顔をして、何のために使うのか分からない別の機器の設定をいじっていた。そして、私に一瞥もくれず、ドアの横の椅子を指差した。
「座れ、喋るな。聞け。"
その男とは反対に、ジムは--初日から彼の姓を使う気にはなれなかった。彼は誰に対してもそうであるように、私に対しても、ただ「ジム」と呼ぶだけだった。その隣で、エスピノザ(ここでは彼女のファーストネームを使う気になれなかった)は唇を鳴らして、明らかにそうではないのに我慢しているように見せようとした。
しばらくすると、画面にオフィスと見覚えのある人物が表示された。エスピノザはにやりと笑った。
"ファーガソン"
"お会いできて嬉しいです、ゲイル "と若い黒人女性はクールに答えた。「そして、ジム。
背の高いネイティブアメリカンは、ただうなずいて了承した。
「さて、それでは。では、お知らせがあります..."
エスピノザがつぶやくと、スクリーンに映し出された女性が続けた。
「マードック氏はあなた方全員に挨拶し、その進歩に満足しています。もうすぐ、あなたたちは彼の伸ばした腕、あるいは握った拳になる準備ができています」。
エスピノザは目を細めて反応し、ジムは不安げに体勢を変え、黙って腕組みをした。
ファーガソンは明らかに気づいていた。"段取りと技術に満足しているのか?"
"まあ..." と言いかけたが、エスピノザの方が状況判断が早かった。
"キャンプも戦車も銃も...""全部ダメだ、ファーガソン "と。戦車は黒く塗られ コヨーテと保安官がいる "報告書はどうだ?"

ファーガソンはため息をついた。
「そうですか、雄弁な報告ありがとうございます、ゲイルさん。では、ひとつひとつ説明していこう。色は......あの戦車は塗り直そう、いいね?帰ってきたらね。ただ......好みとかを書いておいてくれれば、なんとかするよ。技術的なことはまた別だ。幸いなことに...」と、彼女は突然微笑み、「私たちはあなたよりずっと先を行っています。明日、あなたは軍の隣人を訪ねます。そこには、フォート・アーウィンからの贈り物が待っているはずです。マードックさんがお願いしてくれたの、きっと喜んでくれるわ」。
彼女は急に真面目な顔つきになった。
「確かに米軍よりも喜んでいる。だから......事件を起こさないようにするんだ、わかるか?
エスピノザは目を丸くして、口を尖らせ、急に硬い傭兵というより小うるさい女子高生に強く似てきた。
"わかった、何でもいい"
「私は真剣よ、ゲイル」ファーガソンは、まるで自分の意志でその考えを押し付けようとするかのように、身を乗り出してそのことを迫った。「これは私にとっても、彼にとっても重要なことなのです。わかるか?
"はい... ウォーマスター"
ファーガソンは嘲笑し、頭を振って、接続を切った。
"ウォーマスター"?あれは何だったんだ?" 私は不思議に思って尋ねた。
「それが彼女の肩書きなんです。そうなんです、本当なんです」と彼女は微笑んだ。
「マードックはそういう肩書きが好きなんです。その理由は神のみぞ知る、です。ローゼンスタインのように...彼に会ったの?
「そうです。
"彼はスパイ物が好きなんでしょ?内密のブードゥー教とかね "密偵 "みたいなもんだ 今日、普通の人はこれをインテリジェンスと呼ぶ。マードックは違うけど...スパイマスターと呼んでいる"
へえ。私は首を横に振って肩をすくめた。
"よし。じゃあ、"ウォーマスター "は何をするんだ?"
また、にやりと笑った。
"栄光の秘書 "だ。ちょっとした計画を立てると、突然王族のように扱われるんだ、あの女は......"
彼女は立ち止まり、私を見て、ため息をついた。
"いいよ。彼女は自分のことをよく知っている。彼女は自分のことをよく知っていて、教養もある。ただ...彼女は..." 彼女の表情は一瞬よそよそしくなったが、ほとんど即座にそれを止めた。
"もう行こう いつかウォーマスターのことを話してあげるわ...いつか..."
変だな、と思いながら彼女の後をついていくと、日差しの中、また輝かしい修行の日々が始まった。
翌日は、ファーガソンが約束したとおりの面白い日になった。朝、軍のジープがキャンプにやってきて、私とエスピノザを乗せた。さっきの運転手と同じだ。きっと、食物連鎖の上のほうにいる誰かが、彼のことを心底嫌っているに違いないと、私は静かに微笑んだ。
しかし、空軍基地には驚きの光景が待っていた。以前とは違って、文字通り、そこらじゅうが装甲車で埋め尽くされていたのだ。戦車、IFV、APC、装甲車......聞いたこともないようなものが滑走路の周りにずらりと並び、点検を待っている。米軍の兵士たちは、戦車を清掃する者、燃料を補給する者、そしてただ眺める者、さまざまであった。整備小屋の裏から音楽を流している部隊もあり、その光景はまるで巨大な見本市のようだった。
エスピノザも、いつもの嫌味な感じはなく、その喧騒を見つめていた。
「じゃあ、ここで何をすればいいんだ」。
大佐(私は敬礼したい気持ちを抑えていた)と、見覚えのある若くて細い黒人女性である。
エスピノザは不機嫌そうに言った。「足を洗うのにずいぶん時間がかかったね、ファーガソン」。
「ゲイル。会えてうれしいわ。またね」。
彼女は大佐にうなずいたが、大佐は首を振って去っていった。彼女は真剣な表情になった。
"前にも言ったけど、私たちがここにいても誰も喜ばないわ。" "だから、2人とも行儀よくして"
私はただ頷いた。エスピノザの反応は見なかったが、ファーガソンは満足しているようだった。
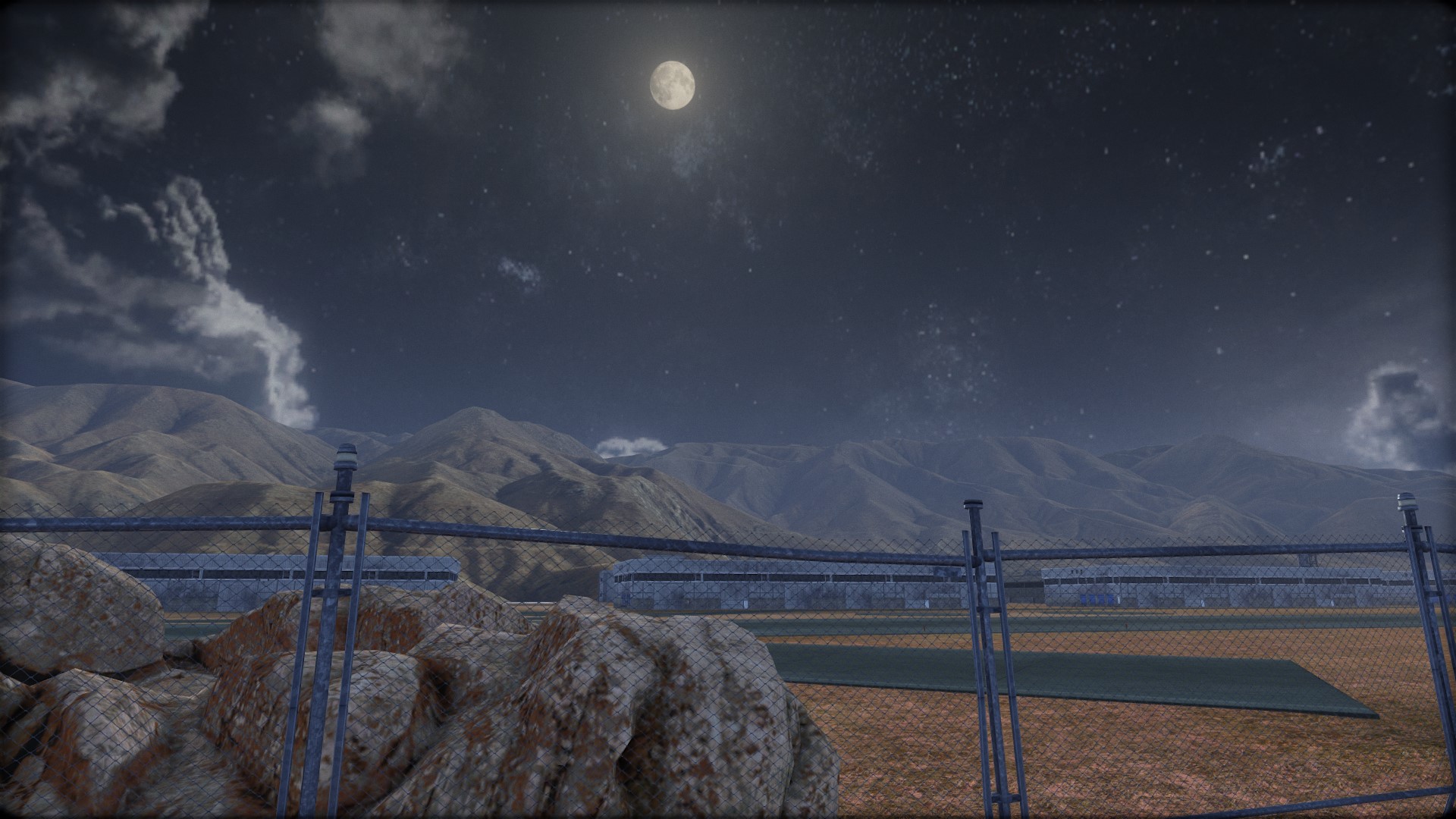
「ご覧のように、マードック氏がいろいろと手を回してくれたので、簡単に言えば、世界中で遭遇する可能性のある、アメリカのあらゆる車両の在庫を限定的に入手できるようになったわけです。アメリカの訓練施設は充実しているから、その恩恵にあずかることができるんだ」。
「とにかく、歩いてみて、興味のある車をいくつか選んで、軍からの一時的な貸し出しを手配しましょう。ただ、あまり無茶をしないようにね。ペリヘリオンの金庫だって、無限じゃないんだから」。
私たち2人にうなずくと、彼女は近くで待っていた大佐と合流した。大佐の表情は険しく、焦りを感じさせる姿勢だった。彼は明らかにその場にいたくなかったが、仕方なくその場にいたのだ。アメリカの大佐を選択の余地のない状況に追い込むには、ファーガソンの主張とは裏腹に、とてつもない影響力、資金、あるいはその両方が必要だったのだろう。
エスピノザは肩をすくめて、好奇心旺盛な兵士の群れの中を進み始めた。週末の戦士のような服装で、あまり目立つことはなかったが、溶け込んでいるわけでもなく、時々、GIジョーから汚い目で見られることもあった。でも、エスピノザはそんなことお構いなしに、まるで駄菓子屋にいる子供のように、次から次へと乗り物に飛び乗った。なぜだかわからないが、彼女が楽しんでいる姿を見ていると、こちらも気分がよくなる。
一方、ファーガソンと大佐はペリヘリオンのカラーリングを施したトラックに移動し、大佐の指示で数人の兵士が高級なハードウェアのような大きな箱を外に運び出し、地下倉庫の入り口と思われる場所に移動しはじめた。
またしても、私は首を横に振った。政治だ。マードックはおそらく、私に知られたくない何かを国境の南側で密輸しているのだろう。
塗装や技術的なことで言い争う俺たちは、まさに安全装置だ。私は、エスピノザの後を追って、苦笑しながらその場へ入っていった。
"さて、何を考えているのでしょう"
この2日間は悪夢のようでした。有望な車を何台か選んで、部隊のチェックのために自分たちのキャンプに移動させた。しかし、ファーガソンの最後の指示は明確で、「ペリヘリオン部隊をどうするか、デビッド・マードックと共同で決定し、提示すること」だった。誰を手放すか、どんな車両、制服、小銃、その他千差万別のものを買うか、そして最も重要なことは、オーバーヘッドだ。
私たちは皆、これは自分たちの給料以上のことだと感じていた。これは、おそらく私たちがどのように課題に取り組み、うまくやっていけるかを見極めるための、もう1つのテストなのだと。もし、そうだとしたら、私たちは「F」をもらうことになる。しかし、私は戦わずにあきらめるつもりはなかった。
「彼女はこめかみをさすりながら、「いくつかの選択肢がある」と言い出した。戦車隊が必要なのは確かだけど......」。
その通りだ。ブラックマンバをあきらめるつもりはない!」。
「...しかし、小型のもので十分でしょう。それから、歩兵がいる、彼らは乗るものが必要だ。APCがいいだろうが、機械化歩兵はいいコンセプトだし、隊員も慣れている。あるいは、「空挺部隊のようにすることもできます。空挺部隊、軽戦車...。アメリカ陸軍のオヤジから、すごいオモチャを買ってきてくれるかもしれないわ」。
私は顔をしかめながら、首を横に振った。
「パンチが必要だと思うんだ。
ゆっくりと、疲れたようにうなずいたのが、彼女の反応だった。
「あのね。そうすれば、やっと本題に入れる。ああ、それとシャツを着替えてくれるかい?その穴は、」彼女は私の腰の近くの裂け目に向かってぼんやりと手を振った、「正確に言うと、"プロフェッショナル "を叫んでいない」。もっといいのがあるでしょ?
私は無心にナイフをいじっていたのをやめ、ナイフをしまった。
「ええ、持っていますよ。私の良いものはすべてダッフルバッグに入っていて、ドバイの高層ビルのふもとのゴミ箱に、他のものと一緒に隠してあるんだ。買い物がしたいんだ」と私はつぶやいた。
「クルマで行こう。歩け。歩いてもいい。ただ、身だしなみを整えるだけでいいんだ」。
「了解です、奥様」私はあざ笑うように敬礼した。しかし、彼女は正しかった。私たちは皆、遅かれ早かれ、しっかりしなければならないのだ。そう思いながら、私はジムを探しに外に出た。
全文はこちらでご覧いただけます。